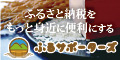お酒の味わい方
トップページ > お酒の楽しみ方
お酒の楽しみ方

理由はよくわかりませんが、神様もお酒が好きだということでしょうか。
お酒は神様と人をつないでくれるものですが、同時に、人と人の間を取り持ってくれるものでもあります。
おいしく楽しいお酒は、社会の潤滑剤です。
テイスティングという言葉を聞いたことのある方は、多いと思います。
いろいろなワインの違いを、香りや色など、五感を駆使して味わおうという方法です。
ソムリエの方やワイン好きの方は、よくテイスティングしています。
その仕方については、ソムリエの方などの動画で知ることができると思います。
ワインばかりではなく、日本酒にも利き酒というのがあります。
蔵元を訪ねたりすると、試飲できるところが多いはずですから、
ただ飲むだけでなく、色や香り、口に含んでその味や口当たりの広がり具合など、幾種類かを利き酒させてもらって比べてみるというのも楽しみの一つです。
お酒の香りを楽しむ方法
香りを楽しむには、3段階あるそうです。- 鼻を近づけたときに漂ってくる「上立ち香(うわだちか)」
- 口に含んだ時に広がる 「含み香(ふくみか)」
- 飲み込んだ後に戻ってくる「残り香(のこりか)」
テイスティングも、プロの方やシェフの方たちの行うのとは違い、仲間内でやってみると、意外と楽しいものです。
やり方としては、複数の種類のお酒を用意して、その違いを飲み比べます。
甘口や辛口、香り、色の違いなどで、それぞれの好みをいい合うのも、楽しみ方の一つになります。
![]()
なじみのラーメン屋さんに行って、また飲み始めたのですが、
仲間の一人の焼鳥屋のマスターが、「ビールはA社のBという銘柄が一番うまい、オレはそれしか飲まん。」と偉そうなことをいったので、
その鼻をへし折ってやろうと近くのコンビニで8種類ほど買ってきて、どれがBか当ててみろと、利きビールをやりました。
もちろん、マスターはBを当てることができませんでした。
面白いのでみんなでやってみたのですが、全然当たりません。
ほとんどがサンザンな結果でした。
半分酔っていたとはいえ、” 違いの分かる男 ” への道は、かなり険しそうです。
グラスを変えて比べてみる
熊本の酒屋さんが、酒処を紹介するTV番組で、同じお酒をグラス(容器)を変えて飲み比べすることをすすめていました。次のような3つのグラスと、あおりの高いお酒を用意します。
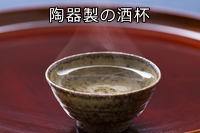


口の中へのお酒の入り方、量が違うことで、受ける印象が異なってきます。
人によって感じ方の差はありますが、やわらか味や辛味の違いが出てくるそうです。
お酒をおいしく飲む方法
お酒をおいしく飲むには、料理と一緒にいただくのがおすすめです。ワインの世界ではマリアージュといって、その組み合わせが大事になります。
ワインばかりでなく、日本酒でもウィスキーでも、料理とマッチした幸福な組み合わせは、
料理とお酒のおいしさが1+1=2ではなく、2+アルファになります。
ご家庭や仲間内で、どのお酒とどの食べ物のマリアージュがあうか、探し出すのもお酒ライフを楽しくしてくれます。
カクテルで意外なおいしさ発見
女性にも飲みやすく、華やかに彩ってくれるカクテルもおすすめですが、ベースとするお酒はリキュールが一般的です。しかし、新しいトレンドとして、日本酒のカクテルがおすすめなのだそうです。
日本酒のアルコール度数は15度前後ですが、カクテルにすることで6,7度に下がり、
日本酒の強さに抵抗を感じていた人にもグッと飲みやすくなります。
新しいスタイルで日本酒と日本酒カクテルの魅力を広げていこうと提案しているバーも、銀座にオープンしているそうです。
ラベルで日本酒を選ぶ面白さ
お酒もジャケット(ラベル)で選ぶ、ジャケ買いが若い人たち、とくに若い女性の間で楽しまれているようです。確かに清酒のラベルは、毛筆風の、フォントに囚われない字体で、特徴や蔵元色を表現する自由体のものが多いようですが、逆に、どれもが同じようなイメージのものばかりになってしまいます。
最近、文字の一切かかれていない、イメージ画像だけのラベルや、
シンプルな線や図形で、現代アートのようなラベルのお酒などが出てきています。
ラベルだけでなく、瓶の形にも、一升瓶タイプばかりでなく、ヴィンテージウィスキーのようなものや、スマートでおしゃれな形のものも造られてきたようです。
もちろんそれらは、奇をてらって作られたわけではなく、お酒の性質を端的に表すものを、自由な発想からデザインしたもののはずです。
ジャケット(ラベル)に、自分のフィーリングと合った何かを感じて飲んでみる、新しい楽しみ方が増えたといえるかもしれません。
お酒を飲むための理由
 お酒を飲むための理由は、無限にあります。
お酒を飲むための理由は、無限にあります。昔、中国に『竹林の七賢』といわれる人たちがいました。
この中に、劉伶という大酒飲みがいました。
この人は、「酒徳頌」というわずか一編の詩を残しただけらしいのですが、その冒頭に述べられていることは、
「大人先生(だいじんせんせい)という者がいて、一日も一万年もほんの一瞬。
大空が屋根で大地が敷物、住居を持たず、世界が自分の家であり、どこに行くにも酒器と酒壺を手放さない、ただひたすらに酒を飲むことだけに精を出した。」
とあり、この酒をたたえる一編の詩だけで、後世に名を残した人だそうです。
大酒のみの劉伶は逸話に事欠かず、ある時彼の妻が酒をやめてほしいと涙ながらに懇願したそうです。
劉伶は神に誓って禁酒するから、そのためのお神酒を持ってくるようにいました。
お神酒が運ばれると、劉伶は、「天は劉伶を生み、酒をもって名を成さしむ」とうそぶいて、お神酒をしこたま飲んで酔っ払ったといいます。
お酒を飲むための理由は、いくらでも見つかるものです。
![]()

ご当地の「お酒&グルメ」をセットで選べる通販【SAKEぐる】!
![]()


お酒の楽しみ方についての関連記事
・日本酒の楽しみ方・焼酎の楽しみ方
・ワインの楽しみ方
・ウィスキーの楽しみ方
・ビールの楽しみ方
・他のお酒の楽しみ方
・カクテルの楽しみ方
![]()
記事の一覧
お酒の種類
醸造酒 / 日本酒 / ワイン / ビール
蒸留酒 / 焼酎 / ウィスキー / ブランデー / スピリッツ / リキュール
お酒の蘊蓄 / お酒トリビア / 珍しいお酒 / お酒と歴史あれこれ / お酒と健康 / お酒と美容
お酒と料理・肴 / お酒をおいしくする器 / お酒をおいしくするグッズ
お酒に関する用語